|
花、花、花 闇に似た“無”に白い欠片がふわふわと舞う。 欠片は雪にも見え花びらにも見え、忙しなく揺れることでその正体を明かさない。 重力などないとばかりに、欠片は空をくるくる回る。あるいは、消える。 消えるより多く、どこからともなく欠片は生まれ、徐々に視界を侵食する。 ぷるん、と、何かが体から離れる振動を感じた。 わたしは、驚いて全身を見下ろすけれども、何かが失われた様子はない。 ふと、前を見ると、良く見知った、けれども知っているはずがない後姿が目に入る。 そのひとは、振り向く素振りも見せずにずんずんと前へ進んで行く。 泣きたくなるほどの喪失感に包まれたけれども、わたしには何もできない。する資格もない。 今や吹雪の如く狂い舞う欠片に閉ざされ、遠くへ消えていく背中を、ただ、眺めていた。 夢はいつもそこで終わる。  花が、笑う。 限界まで咲き、花弁が零れんばかりの状態をそう言うのだと、彼が教えてくれた。 じゃあ、今この桜並木は絶賛大爆笑中ね! 少しケチをつけるように、でもとても楽しそうに、涼宮さんは笑った。 綺麗ですねぇ。 朝比奈先輩は、可愛らしい声でほっこりと微笑んだ。 古泉さんはただにこにこと涼宮さんの後ろを歩いている。 わたしは古泉さんのことはあまり得意ではないので、近付かれると萎縮してしまう。古泉さんもそれを分かっているので、極力わたしから離れてくれる。少しだけ申し訳なく、随分ありがたかった。 長門、寒くないか? 彼が穏やかな声で聞いてくれる。わたしは首を振った後、思い直して「ない」と小声で付け足した。 そうか、でも気をつけろよ、風は強いし春とは名のみの冷たさだ、油断すると風邪を引くぞ。 彼の声は落ち着いていてとても安心する。 昔から、人とコミュニケーションをとるのが苦手だったわたし、友人と呼べる近しい人でもきちんとした応対は出来ないし、まして、男の人だなんて怖いだけだったけれども、彼のことは何故かしら平気だった。勿論、涼宮さんや朝比奈先輩のように、なめらかな会話は出来ないけれど、彼はわたしを急かすことなく優しい目で待っていてくれるので、話をしよう、ついて行こうという気持ちになれた。 彼だけじゃない。このひとたちは、誰もわたしを邪険にしないし、逆に、期待しすぎもしない。わたしの手を取ってくれるけれど、無理矢理引きずって行こうとはしない。 とても居心地の良い空間。そして、ひと。 光陽園学院の、涼宮さんと古泉さん、一学年上の朝比奈先輩と違うクラスの彼と、わたしが、“団活”と称する集会をするようになったのは、とても不思議な、ある出来事が発端だった。 去年の12月、心の暦に刻み込まれて仄かに光る、18日。わたしは、いつものように文芸部室で独り本を読んでいた。高校に入学してから9ヵ月、十年一日の如き変化のないいつも通りの放課後に、彼が飛び込んできた。 その彼は実はこの世界の彼ではない、異世界から来た彼だったけれど、その時わたしには少しも区別はついていなかった。 彼はほんの僅かな時間でわたしを、今まで経験したことのなかった嵐に巻き込んだ。 巻き込んで、だのにいきなり消えた。 翌々日、彼は、わたしに、前の日にわたしが手渡した入部届けを差し返した。自分の世界はここではないから、と。 そしてそれを証明するように、彼はわたし達の目の前で、こつぜんと姿を消した。 残されたわたし。 しんとした部室。 ああ、これで終わってしまった。 彼が消え、一瞬で彩度が落ちた部室で、私は真っ先にそう思った。心に、ぽっかりと空洞が生まれたと感じた。 三日間、それまでの人生で経験したより多くの出来事があった。 部室の扉が音を発てて開き彼が飛び込んできた。お前は本当は宇宙人だと言われた。男のひとに、初めて肩をつかまれて揺さぶられた。決死の思いで彼を部屋に誘った。彼と、おでんを食べた。 それまでの思い出が全て霞むくらい、強烈で、ありえないことで、…楽しかった。 彼が消えて、ああ、この非日常も終わってしまったのだと寂しく思ったのだけれども。 「…ちょっと!今の、何?何が起こったのよ!?ジョンは?あんたたち、ジョンが何処に消えたか見た!?」 彼以上に不可解な人物、何の挨拶もなくわたしの空間に乗り込んできた人が声をあげた。それが、涼宮さん。彼と共にやってきた、こちらの世界の知らない人。 彼女はわたしと違って全く諦めてはおらず、その後の事態も、中軸は涼宮さんに移ったけれども、同じ程度に怒涛の変化を遂げた。 彼が自分の世界に帰った、と判断した涼宮さんは、次の日には“こちらの世界の彼”とコンタクトを取り、戸惑うわたしたちを有無を言わさず引き込んで「本家SOS団」を結成した。「時間移動や超能力てな不思議が溢れる向こうより、平々凡々なこの世界で不思議を探す方が純粋かつ困難で、高尚だものね!」というのが「本家」と冠付けた理由だそうだ。わたしには良く分からない理論だったけれど、それでも、グループを一つまとめ上げてしまった涼宮さんは凄いと思った。 「有希!早くいらっしゃい!風が気持ち良いわよ!」 長い髪をたなびかせて、花よりも軽やかに涼宮さんが笑う。はためくスカートの裾を押さえもせず颯爽と土手を駆け上がる。姫の手を引く騎士になり損ねた古泉さんが慌てて後を追う。ふわふわと、綿帽子が転がるように朝比奈先輩が草を踏む。遅れているわたしがはぐれないよう、ゆったりと彼が肩を並べる。 手招きするかのようにさわさわ揺れる桜の枝に誘われて土手を上がったけれど、涼宮さんたちはずっと離れた河川敷に移動していた。 「桜は綺麗だけど、こう花が笑っていたら折角のお弁当が花びらだらけになっちゃうからね!花は少し離れた所から見る方が風情があると言うし、ここにしましょう!」 ばんっ、と、音を発ててレジャーシートを広げる。わざとではないだろうに、角が彼を直撃して彼が抗議する。 勿論、涼宮さんは気にしない。 「キョン、うっさい!」「ドジねぇ!それくらい避けなさいよ!」 口調はきついけれども、とても楽しそうだったし、彼もそんな涼宮さんを許容していて目尻は優しい。 「んー!みくるちゃんのお弁当は最高ね!ほら有希!早く座って食べなさい!じゃないと男共に食い尽くされるわよ!」 「一番食うのはお前だろうが!」 とても騒がしいのに周囲の空気は穏やかだ。 「でも本当、晴れて良かったわ!絶好のお花見日和よね!去年は途中から雨に降られて散々だったものね!」 あれはあれで楽しかった。 同じメンバーで花見に出かけ、やっぱりこうやってお弁当を広げて半分くらい食べたところで雨が降ってきた。 わたしたちは大慌てで荷物を片付け大きな木の下まで走って、そこで、雨宿りをした。 濡れて凍えた体を寄せ合い、雨に光る花弁を見上げた。わたしにとって、それも、とても綺麗な思い出だった。 「じゃあ、今日はこれで解散!有希、みくるちゃん、キョン、また来週ね!キョン、あんた有希を送って行きなさい!」 夕刻、涼宮さんの号令で解散。楽しい時間はすぐ過ぎてしまう。 彼は当たり前のようにわたしの横に並び、わたしの歩調にあわせて足を運ぶ。 さっきまでは先に行く涼宮さんたちとわたしを繋ぐ位置にいたので、彼の足取りは涼宮さんの速さとわたしの鈍さの両方に引っ張られてバタバタしていたし、口調も、涼宮さんに向けて怒鳴り朝比奈先輩に向けて華やぎもし忙しなかったけれど、今はただ、わたしだけに合わせて小川のせせらぎのように穏やかだった。 このひとは、去年の5月、図書館で戸惑うわたしに代わって図書カードを作ってくれたひと。 去年の12月に、いきなり部室に飛び込んできて、意味不明な行動をとって、結果、わたしと涼宮さんたちを引き合わせたひととは別のひと。 このひとによると、異世界から来た彼がわたしたちの前にいた時は、風邪で学校を休んでいたのだそうだ。それは、本当。涼宮さんが彼の家の人に確認していた。 「ってもな」 複雑な表情で、彼は後になってうち明けた。 「何でかその三日間、俺の記憶はあやふやなんだ。大して熱はなかったし意識が飛ぶほど重体だったわけじゃないのに、良く思い出せないんだ」 それは異世界同位体が同一の空間に存在していたことによる歪みが原因よ!あんたの意識はもう一人のあんた…、ジョンが主体として行動することによって吸い上げられていたのよ! 涼宮さんは嬉しそうに叫んだ。 何の根拠もないことだった。けれども、みんな、少なくとも私は、すぐに納得した。 彼はわたしをマンションの前まで送ると、じゃあと手を振り遠ざかってゆく。 わたしは引き留めたいのに声も手も出ない。 上がって、お茶でも飲んで行って。 そう言いたいのに口に出せない。 あの時は、引き留めて誘えたのに。あのひとも、誘いに乗ってくれたのに。 …でもきっと、彼は断るだろう。女の子の独り暮らしの部屋にのこのこ上がるほど、気の回らないひとではない。同じ彼だけれども、きっと違う。あの時は彼はどうかしていたのだ。寂しくて、心細くて、誰かに縋りたかった。わたしもその気持ちが分かったから、彼の袖を引けたのだ。 でも今の彼は、寂しいひとではない。 それにわたしも。 わたしもあの時とは違う。今のわたし達は、引き留めなければつなぎ止められない関係ではない。また会える。明日も、来週も。 だから、わざわざ引き留める必要は、ない。 「…ただいま…」 誰かが出迎えてくれるわけではないけれど、そう声に出してから部屋に入る。 何もない、がらんとした部屋。 ときどき五階の朝倉さんが晩御飯を持ってきてくれたりするけれど、基本はわたししかいない、しんとした空間。 昔からそう。 ずっと、そう。 …だのに最近、胸が締め付けられ泣きたくなる。 何も、ない。 飾りたいわけではない。やみくもに何かが欲しいわけでも。 ただ、何かが足りない。大事なものが欠けている。此処には………が、ない。 鬱陶しいくらいにわき上がる、喪失感。 普段は気付かないふりをしているけれど、時々捕まってしまう。わたしの心は涙を流すけれども、わたしはそれを自嘲する。 何を亡くしたというの?元々あなたは何も持っていないじゃない。 あなたは勘違いしているだけ。 涼宮さんたち、仲間と呼びたいひとが出来てから、欲張りになっているだけ。魅力的な友人が出来たのを自分の手柄と思い違えて、自分にも何かあるに違いないと、勝手な妄想を広げているだけ。 もっと持っているはずだなんて図々しい。あなたには、何もない。今、周りにある、それがあなたの全て。 自重しなさい、長門有希。 手元にある、それがあなたの全て。欲張ってそれすら逃してしまうことのないよう…。 来客を告げるインタフォンが鳴り、思考を遮られてびくりとする。 玄関ではなく、エントランスホールの、外からの来客を告げる音だった。 心当たりはなかったけれど、回線を開く。 『長門、俺だ。今、良いか?』 「…」 彼の声だった。 さっき別れたばかりのあのひと。この独特な穏やかな声を、機械越しでも間違うはずがない。 何か忘れ物でもしたのだろうか? 『ちょっと話があるんだ。上げてもらえないか』 すまなさそうな、でも断固とした声。 少し驚いたけれども、ロックを解除するのは迷わなかった。 エントランスのロックを外した後、わたしも部屋を出る。 屋上で会おう。 彼がそう指定した。 また星を見上げるのだろうか。夏休み、みんなで観測会をして時のように。…まさか。 何故屋上か、そもそも何故訪ねて来たのか、わたしには分からなかったけれど、彼のすることはわたしごときの考えは及ばないし、いつだって正しい。 屋上に出ると、日が落ちたばかりの、薄墨色の空に迎えられる。 「よ、長門」 中央に立つ、そのひとに歩み寄ろうとして止まる。その輪郭に違和感を憶え、ざわざわと、胸騒ぎがする。 「こんばんは、長門さん」 彼の影に重なっていた人が、彼から分離するようにして現れた。 「…え…?」 「…あー、すまん、長門。どうしても付いてくるって言って止められなかった。…それに、もしかしたらこいつの方がちゃんと説明出来るかもしれん。ちょっと我慢してくれ」 「酷いな、僕は邪魔者ですか?」 「取り敢えずはな。長門が怯える。暫く向こうへ行ってろ、古泉」 何故古泉さんが此処に?彼とはそんな、課外活動が終わってからも行動を共にするほど仲が良かっただろうか? …ううん、そこじゃない。さっきから感じている違和感の正体はそこではなく…。 古泉さんは肩を竦めて数歩後ろに下がる。薄闇がその全身を飲み込んだ。 あらためて、彼が私の方を向く。 「久しぶりだったな、長門。元気だったか?」 何を言っているのだろう、この人は。さっき別れたばかりじゃないか。おかしなことを言う。 頭の中ではクエスチョンマークをいっぱい浮かべていたけれども、ううん、分かっている。違和感の正体に、ちゃんと気が付いている。ただ 「何て言ったらいいかな。…その、長門、俺はこの世界の人間じゃない。あの時の…、ジョン・スミスなんだ」 ただ、認めたくなかっただけだ。今この日常を壊すものは。 たとえそれが、今のこの穏やかな日々をもたらしてくれたひとであっても。  座って話さないかと彼が言ったので、フェンスの土台に並んで腰掛ける。 常夜灯の灯りが彼の姿を浮かび上がらせる。 同じひとだけれど、違う。雰囲気や服装だけでない。目の前のひとは、私が知っている彼より、いくらか背が高く、顔立ちも大人びていた。 このひとは、彼ではない。先程マンションの前で別れた同級生でもなければ、冬、私の前から消えた異世界の彼とも厳密には違う。 何から話そうか。 彼は、優しい形の眉を歪めて言いよどむ。 うん、ちょっと説明しにくいし、理解出来ないかもしれないが、取り敢えず聞いてくれ。 歯切れ悪く、でもしっかりと私を見た。 「何が正解で何が誤りかなんて言い方はしたくない。ある人にとっては正しいことでも、別の人間が違う角度から見れば間違っているってことはあるからな。…だが、あえて言わせてもらう。長門、この世界は間違った世界なんだ」 間違っている?一体何が? 「詳しい説明をする前に一つ聞きたい。長門、お前は俺のことをどこまで理解している?俺を何だと思っている?いや、長門自身がでなくて良い、こっちでもSOS団ができたんだろ?こっちのハルヒ…お前たちは、俺達の世界を何だと認識している?」 「…わたしは…」 わたし自身が彼から聞いたことはとても少ない。「お前は宇宙人だ」と断言され、詰め寄られた。 でもわたしが彼が思う通りの人間ではないと知ると、彼はそれ以上は語らなかった。 翌々日、涼宮さんたちと乗り込んできた時にも何も語らず消えて、後になって涼宮さんから、あれは平行世界から来た異世界人よ、と、教えられた。その世界では、涼宮さんが神に等しき超人、朝比奈先輩が未来人、古泉さんが超能力者、そして私が宇宙人製のアンドロイドだと、彼から聞いた話として伝えられた。 つまりパラレルワールドってわけ!向こうはすっごく楽しい世界みたいよ!ねえ、こっちでもあたしたち、SOS団を結成して楽しいことをしましょう!…ね、ジョンってこっちにも居るの?ジョンじゃなくてキョン?一緒よ一緒!…居るのね?どういう位置付けなのかしら?こっちにジョンが居た時はどうしていたのかしら?ちょっと捕まえて聞いてみましょう! そのまま彼の家に突撃しそうな雰囲気だったけれど、古泉さんが止めた。 捕まえるって、彼の家をご存知ですか?もう夕刻ですし、行動を起こすにしても明日にしませんか?先ず、今後の対策を練りましょう。等々。 その結果、行動開始は翌日から。“彼”の捕獲はわたしに命ぜられた。 放課後、あたしたちは授業が終わり次第北高に行くから、校門前で待っているから、キョンを連れてきて頂戴!…何て言って連れて来れば良いか分からない?あたしがちゃんと説明するから!有希はあいつを連れてくるだけで良いの! その、連れてくるだけ、が、どれだけ大変か思いもしないバイタリティのある彼女は、わたしに反論する隙も与えてくれなかった。 多分、わたしが凄く情けない顔をしていたからだろう、朝比奈先輩が、不安をいっぱい浮かべた顔で「あたしも協力しましょうか?」と申し出てくれた。 次の日、どんな思いで、どんな方法で彼を捕まえたのか、実は良く憶えていない。彼なんか居なければいい、いや、いてくれないと困ると、相反する思いを抱え、申し合わせた朝比奈先輩と5組に赴き…。…同じ5組の朝倉さんが協力してくれたような気がする。 前日のことなどまるで知らない、だのに前日のそのひとと同じ顔をした彼は、何の用か全く見当の付かない顔でわたしたちを見下ろした。 「“キョン”はあっさり信じて仲間になったのか?」 「…最初の説明では、あまり。でも、彼がいなかったはずの三日間、あのひとは確かにいた。クラスの人や周りの人、彼に嘘を吐くはずのない人たち誰もがそれを証明した」 マジかよ…。 一通り検証したあと、彼が呟いた、呆然とした、囁くような声は今でも思い出せる。 彼は、信じるとも信じないとも言わなかった。 『その件は保留する。で、お前はこっちの世界でもSOS団を結成して遊ぼうってんだな?』 そっちは面白そうだから、ノる。 その言葉が、本家SOS団結成の合図となった。 「つまり長門は、あの時俺が残した情報と、それを元にした憶測以外にこの世界のことを知らないってことだな?」 「…」 探りを入れる真剣な眼差しが何を言いたいのか分からなかったけれども、その通りなので頷く。 彼はどこか寂しそうに笑って、そっか、と囁いた。 「長門、よく聞いてくれ」 意を決した強い声で、彼は私を真っ直ぐ見つめる。知らず、私は居住まいを正す。何を言われるのか分からなかったけれども、何を言われるにしても真剣に聞こうと思った。 「この世界は俺達の世界の平行世界じゃない。独立した世界ですらない。この世界は…、俺達の世界の一部がはみ出て構成された、断片世界なんだ」 そんな言葉で、彼は、この世界の成り立ちを話し始めた。 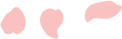 自分で言うのはちょっと恥ずかしいけれど、わたしは、SFに関してはそこそこの造詣がある。 小説は、日本のもの海外もの取り混ぜ古典も新作もかなりの数を読み込んでいるし、誰にも内緒で書いている小説の何作かのジャンルはSFだ。 彼がいきなり部室に飛び込んで来たあの日、思い付いた妄想は、恋愛ものではなくSFだった。涼宮さんが話してくれた異世界の話もすんなりと飲み込めたし、多分、わたしが一番信じている。 だから、彼の話してくれた“真実”、この世界が出来た経緯も、認めるとは別の脳で、すぐに理解出来た。 この世界は、異常作動した“長門有希”が、“涼宮ハルヒ”の力を借りて作り上げた、“長門有希”が望んだ世界。 不可思議事の何もない、ただ優しい友と環境に囲まれて平凡に過ごしたい孤独なアンドロイドが見た夢の世界。 でもそれだと全部は上手く説明できない。 「じゃあ何故、この世界は在るの?あなたの話だと、この世界とあなたの世界は同一のもの。あなたの世界が戻ったのならこの世界は消えているはず。…何故?」 「さすが長門、鋭いな」 この程度のこと、褒められるものでもない。 「世界が戻った時、こっちの世界は切り離されてしまったんだ。だが、パラレルワールドとしてじゃない。ある一部の機能を秘匿する為のクローゼットとしてだ」 「クローゼットというよりゴミ箱でしょう。彼女は不要と判断して捨てたのですから」 いきなり、いつの間にか彼の隣、フェンスに寄りかかっていた古泉さんが割り込んできた。彼は気に入らなかったらしく、舌打ちをする。 「古泉!余計な口を挟むな!」 「余計ではありませんよ。あなた、先ほどから長門さんを傷付けまいとするあまり、言葉を選びすぎて話が回りくどくなりすぎています。僕は長門さんに理路整然と説明をする役として帯同を許されたのですから、此処こそ僕の出番だと思いますけど?」 「それは俺の説明で長門が理解できなかったら捕捉してくれということだ」 「…古泉さん、話して」 「…長門さん?」 「長門…」 彼が話し難そうだったので、思わず割って入った。 古泉さんが話したいのなら、そうした方が効率的だと思ったのだ。 彼はとても優しい。わたしみたいなものにも、とても気を使ってくれる。傷付かないよう、怯えさせないよう、まるで、彼にとって大切なものだと勘違いしてしまいそうになるくらいに。 彼はわたしを傷付けない。だから、わたしに振り下ろされる刃があるのなら、それが避けられないものならば、彼以外の人の手で。 そう思って、古泉さんを見る。初めて、真っ直ぐに見て、驚く。 この人はこんなにたおやかな人だっただろうか。 元々、誰にでも敬語で接する丁寧な人で、感情を荒げたことがなく、一歩離れたところから涼宮さんやわたし達を見守る大人びた人ではあった。 けれどもそれは、あくまで高校生にしては、ということで、大人の自分を演じている、背伸びをしている部分もある人だった。だからこそわたしという腫れ物に、一歩引いて触らないことで対応していたのだ。優しさもあるけれど、はっきり、わたしを持て余していた。 でも今目の前に立つこの人からは、自然な包容力しか感じない。わたしの欠点、どうしようもないところを了解して、見守ってくれている心の広さを感じる。 それに、こんな容姿だっただろうか。確かに古泉さんなのだけれど、昼間会った人より大人びて見える。髪も少し短いような…。古泉さんの顔はいつも目の端で捉えるだけで直視していなかったから、確かにそうだとは言えないのだけれど。 「僕の顔が不思議ですか?」 思っていたことを言い当てられて思わず俯いた。でも古泉さんはまるで気にしていないようで、柔らかく微笑んでわたしと彼の前に、小さな子供に目線を合わせるようにして腰を降ろした。 「かまいませんよ、当然ですから。 僕は長門さんの知っている古泉一樹とは別人ですから。…違う世界から来たという意味だけでなく。 長門さん、この世界は僕たちの世界が亡くした一部なのですよ。亡くした、というか意図的に捨てられた、が正しいですけどね。世界を構成するのに不要と捨てられた断片なのです。もっと正確に言うならば、捨てた断片を、捨てたまま活かしておく為に、作られた世界なのです」 「…」 「誰が捨てた何かは、聡明なあなたのことですからお分かりかと思いますが」 「…なにを…」 そんなことを言われて分かるわけがない。何かを捨てる為に世界を一つ作っただなんて。それが誰か、など。 そう言いたいところだったけれど、残念なことに、わたしはそこまで厚顔ではない。先程聞いたこの世界の成り立ち、とりまく人々を思えば自ずと答えは出る。 それに、わたしであればこそ、分かる。他の誰が分からなくても、わたしは。 「お分かりでしょう?捨てたのは長門さん、そして捨てられた一部があなたです」 地面が消失する。 闇の中。 ちらつき出した欠片の中、目の前に立つのはわたし。 人形と等しく、何も宿さぬ目で、お前でもあるわたしを見る。 わたしではないかのように、わたしを。 きびすを返し、何の哀惜もなく置いていく。 痛み、哀しみ、愛慕、悔恨。 彼女はなにも持ち合わせていない。 何故ならば。 古泉さんは少しだけ沈黙で間を作り、困ったように笑って小首を傾げた。 「長門さんが捨てたのは、あなた…、長門さんの“感情”です。そしてそのあなたをまるごと閉じこめる為に作られたのがこの世界です。 長門さんは、情報統合思念体により作られたTFEI端末…、アンドロイドであり涼宮さんの観測という任務を与えられた作り物でした。淡々と、命ぜられた仕事をこなす機械のようなものです。 そんな長門さんでしたが、経験を重ねるうち、徐々に自我に目覚めました。俗に言う、感情というものを持つようになったのです。ですがそれは、創造主から与えられた任務、涼宮さんの観測を粛々と遂行していく上では障害となるものでした。…少なくとも長門さんはそう“思い”ました」 「バグだ、と言ったんだ、長門は。俺は世界改変を強行したあいつの行動の元となったものを、バグではなく感情ってヤツだと見抜いたが、こういう世界であれば良いという願望を叶えたくらいにしか思っていなかった。…だが長門の思惑は、俺の推測なんぞ軽く超えていた」 彼が横から口を挟む。主導権を取り戻そうとしたのではないらしい。古泉さんの言葉では足りない部分を捕捉したかったのだろう。 「長門は、自分がバグと呼んだものの正体は感情であると分かっていた。己に宿ったそれを感情と認めた上でバグであると断じたんだ。ハルヒの観測者として自分には不要どころか邪魔なものである、ってな。だが生まれてしまったものは無に帰すことは出来ない。戻せないが要らない。そう思った長門は 「戻せないなら捨てれば良いとこの世界を作りました。長門さんによる世界の改変、それは己の境遇を嘆いた長門さんがかくありなんと望んで成されたのではなく、初めから、あなた…自分の感情を捨てるダストシュートを作る為の大がかりな仕掛けだったのです。 何故、感情を切り離すのにこれだけ大きな箱を用意したのか、長門さんは教えて下さいませんでしたので、僕たちの推測ですが、一つは、長門さんの感情というものが小さな箱では収まりきらなくなったほど大きくなってしまっていたこと、また一つに、ただ閉じこめておくだけでは発散の場のなくなった感情が独自進化を遂げるのではないかと危ぶんだのではないかということ。長門さんにとって感情とは予期出来ぬ制御不能のものです。自身が置かれているものと同等の環境の、より平和な箱の中に置くことで、変化予測を容易にするという対処を選択されたのでしょう。 そしてもう一つは、僕たちはこの意味合いが最も強いと勝手に思っているのですが、あなた…“感情”に対する憐憫があったのではないか、ということです。自分の都合で排除し、進化を停止させてしまった、その感情のどこかに「普通の高校生活を送りたい」という願望も確かにあったのでしょう。その望みを叶える為もあって、この吹き溜まり世界を作ったのだと思います」 「改変世界の修正是非の選択は俺に委ねられていた。俺が世界を戻すかどうか決めろと言われたのだと思っていたが、あれは長門のミスリードだ。力のないハルヒが居る世界など、長門に作ることが出来ても情報統合思念体が許すはずがない。ハナから長門は俺が改変世界の修正…分離を遂行することは計算に入れていたんだ。何でそんな手間をかけなきゃならなかったのか、俺のこのアナログな頭じゃ理解できんがな、世界を一つ作るってことはそれだけ大仕事ってことなんだろう。後に最も傷跡を残さない外科手術方法だったということだ」 そして、沈黙。 彼も古泉さんもわたしの反応を見る。 けど、何を返せば良い? ここが、彼らの世界の平行宇宙ではなく、イレギュラーだとして?わたしが、人ではなく、“長門有希”の感情を具現化した存在だとして? 他の人にとってどうかではない。この世界が元からあったのか誰かの意志により作られたのかも関係ない。わたしはわたしだし、わたしにとって、わたしも、この世界も、あのひと達の笑顔も手の温もりも本物だ。本物だけれども……………。 夜風が、ざわりと全身を撫でる。 「長門さん、あなたがこの人に会ったのは…この人が消えたことによりこちらにもSOS団が結成されたのはいつのことです?」 「…え、…き、去年の…、12月…」 いきなりの問いかけに、意味も分からず返すと、古泉さんは少し哀しそうに首を傾げた。 「今日、花見に行かれたのですよね?今年の桜はどうでしたか?」 …今年の桜は…とても綺麗で、天気も良かったからお花見は楽しく平和に終わった。でも、雨に降られた去年も、それはそれで楽しくて………、…去年? わたしをずっと見つめていた古泉さんが、顔に刻んだ哀れみを深くして、微笑んだ。 「みんなで夏祭りにも行きましたよね?長門さんは彼にお面を買ってもらった?」 「…」 闇夜に咲く、刹那の花。 まやかしの、大音響とともに、一瞬で散る徒花。 なかなか豪快じゃない!町内会主催の癖に、よくやってるわ!と、涼宮さんが笑う。綺麗ですねぇ、と朝比奈先輩は頬を染めた。彼と古泉さんは、何も言わないけれど、同じように口元を綻ばせて空を見上げていた。 とても大切な、夏の思い出。 「もう一度聞きます。長門さん、涼宮さんたちと初めてあったのは、いつの12月ですか?」 「…」 聞いたのに、古泉さんは答えを待ってはいなかった。わたしの顔に正解を見たからかもしれない。 「この世界は、延々同じ時を繰り返しているのです。正確に言うと、SOS団が結成されて、お互いの距離が安定し、活動が軌道に乗った4月から一年です。 あの日からそれまで…、世界改変 僕たちはかつて、涼宮さんの力により夏休みの後半二週間を一万回以上繰り返しました。ですがあれとはまた特性が違います。あの夏の繰り返しは記憶のリセットがされ、それ以前のものはなかったことにして一からやり直しを強いられました。 ですがこの世界の繰り返しは蓄積されています。長門さんだけでなく、涼宮さんも、こちらの僕も、この人も“去年”の記憶を持ったまま“今年”を過ごし何の疑問を持たない。再び高二の一年を繰り返しているというのに、です。 そうですね、丁度、ギャグ漫画によく用いられる手法で、サザエさんワールドとか、のび太くんワールドとか言われるように、何度季節が巡っても登場人物の年は取らない、あれと同じ感じですね」 「喩えが悪趣味だぞ、古泉」 「そうですか?この上なく分かり易いと思いますけどね。 兎に角、長門さん、あなた達の春は今年で三巡目です」 あら、こっちの方が見晴らしは良いわね。さっき休んだところの木の方が立派だけど、真下だとその良さが良く分からなかったわ。来年は此処でお花見をしましょう。 一昨年涼宮さんはそう言ったのだ。三回目にしてわたし達はようやく、申し分のないお花見をすることができた。何の疑問も抱かず、三度目の高二の春を…。 ああ、このひとたちは、三年後の彼らなのだ 穏やかな目、ほんの少し高い目線、大人びた面差し。三年分順当に齢を重ねてきたのだ、この人たちは。 「何故?」 どうして此処に来たの?ゴミは不要だからゴミ。捨てた後に気にするものではないはずだ。こちらが何度同じ時を繰り返しても構わないはず、いいえ、わざとそうするように作られたはず。何故、今更。 「それはですね」 「俺が話す、古泉。 長門、あれから三年が経ったんだ。長門…俺達の世界の長門有希も三年分の成長をした。感情をバグとして切り捨ててから三年、あいつはあいつなりに成長して遅まきながら自分の取った行動の誤りに気が付いたんだ。感情はバグではなく、人として成長する過程に必ず生まれるもので、人という形式でハルヒの傍にいて観測を続ける為には不可欠のものだ、ってな。 一度は捨てたが長門はお前を取り戻す必要があると思い直した。その段階になって初めて長門は俺にあの時の世界改変と修復の本当の意味と、この世界のことを教えたんだ。俺達の時間にして昨日のことだ。 『わたしの過誤から放逐したものを取り戻しに行く』ってな。 その作業自体に俺が手伝えることはないし、そう難しいことではないらしい。何かをアドバイスする身分でもない。ただ、利用した俺への謝罪と、三年間手放していた感情が戻った時、自分自身がどうなるかが分からないから、何かあった時のフォローを頼まれた。 俺に拒否権はないし、長門の選択は間違っていないと思う。さっきも言ったがこの世界は間違っている。自分から感情を切り離し、その感情部分だけで、延々と同じ時代を繰り返すなんて不毛も良いところだからな。 だから俺は口出しする立場じゃないが、一つだけ、事を成す前にお前にきっちり説明してからにしろ、と要求した。 話したからってどうなるわけじゃない。お前が理解しなくても、また、理解して拒絶したとしても強行すると長門は言った。もしかしたら知らずにいたままの方が良かったかもしれない。だが俺は知って欲しかったんだ。お前自身が何者なのか、ってことを。 …で、長門じゃ上手く説明出来ないかもしれないし、同じ顔の人間がいきなり目の前に現れたらお前が驚くかもしれないと思って俺が来た。 ああ、古泉はおまけだ。事後のフォローを一緒にしてくれと事情を話したらついてくると言って聞かなかったんだ」 「説明役として、少しはお役に立てたと自賛しておりますが?」 「…。…長門、俺の言っていることは分かったか?」 「…そう」 分かった、でも分からない、でもない、曖昧な応え。 そう、そう、そう。 そう、そうだったの、わたしは。 わたしは、人として大事なものが欠けていると、ずっと感じていた。 ずっと、何かを探していた。探す何かなど初めからないのではないかと思いつつも、ずっと。 足が、バネのように伸び、自然に立ち上がった。あてなどなく、すっかり日が落ちた辺りを見渡す。釣られるように、彼も、古泉さんも立ち上がる。 「…で、だ。長門…、その…」 それまで、深い湖面のようだった彼の瞳が揺れる。 このひとの瞳が揺れるのは、自分が揺らいでいる時ではない。不安定なものをどう受け止めるか思いやる時だ。 「選択肢はない、と言ったが、長門、実のところお前はどうしたい?…その、このままで居たいとか…」 「…そう言ったら、あなたは叶えてくれるの?」 見上げると彼はあからさまに狼狽えた。くすり、と古泉さんが笑う気配がしたけれど、わたしの視界には入らない。 彼は、優しい。 その優しさは、思ってもいない我が儘を紡がせてしまう。 「…それは、だな、長門。完全に希望に添うことは出来なくても…」 「下がって」 わたしの声が彼の後ろの闇から聞こえた。 仄かな青い光が徐々に輪郭を成し、彼の前に出る。 「…長門…」 わたしがいた。 わたしではない、わたしより欠けているところが少ないわたしが。 彼女は滑るように音もなくわたしに歩み寄る。感情をこそぎ取られた目で私を見つめる。 「あなたは、誰?」 問う。 疑問ではなく、確認。 「わたしは、情報統合思念体によって創られた、対人類コミュニケート用ヒューマノイドタイプインターフェース。…長門有希」 「何故、ここに来たの?」 「ミステイクの修正の為」 「…」 「わたしは、涼宮ハルヒの観測を目的として創られた。涼宮ハルヒの観測はわたしの絶対の使命であり唯一の存在意義である。その任務を妨害するあらゆる要因は排除せねばならない。 三年前、わたしはわたしの中に任務に支障をきたすバグを発見し、排除した。 それが、あなた。“感情”と呼ばれるもの。 わたしは当時、任務の為には感情は阻害因子と判断した。 だがそれは過誤であったと修正認識した。存在形式を人とした以上、人間が当然具える感情を持ち、コントロールしなければ効果は半減する。 だから、来た」 「…わたしを…、この世界を消すの…?」 「元々こちらの一部。復元と言う方が正しい」 「長門!もう少し…」 「この世界の他の人は?わたしはあなたの一部だけれども、涼宮さんは?あのひとたちはどうなの?」 「あなた以外の人間はあなたが作った。あの人たちの記憶を持つ私の一部であるあなたが、その記憶の中から拾い上げ具現化した、あなたの内包物。したがって復元後はあなた、ひいてはわたしに戻る」 「…そう…」 途中で口を挟みかけた彼は、わたしたちの様子を見て口を噤んで一歩引いた。 それで良い。彼の事は大事で好きだけれど、今はわたしたちの間に入り込んでもらいたくはない。 わたしがどうするのか、多分誰でも知っている。わたし自身ですら。 それでも。 「何故、来たの?」 もう一度、問う。 疑問ではなく、確認。 彼女は数ミクロンばかり小首を傾げた。瞳の色が深みを増す。 「わたしには、あなたが必要」 光が、弾けた。 白い欠片がくるくると舞い、去ったはずの背中が近付いてくる。 欠片が、渦を成し世界を包む。 あらゆるものが渦巻き、注ぎ、私を侵食し  いきなり天地がひっくり返ったような衝撃に襲われたかと思ったら、一瞬後、俺は土の上に尻餅をついていた。長門のマンションの屋上にいたはずだったが…。 夜陰に包まれてはいるが、街頭と月明かりとでそこそこ視界はきく。 用心して見渡すと、風景に見覚えがある。馴染みの、川沿いの桜並木の下だった。 帰って来た…んだろうな。でもって帰ってきたということは、終わったということか。 月は真上だ。俺たちが長門の内面世界へと発った時と場所は移動したが時間は大して経っていないらしい。 出発地点は長門の部屋だった。 三年前、切り捨てたわたしを回収しに行く、と言われた。 長門がしでかした三年前の世界改変、あれは、長門自身がバグと判断した己の一部分を封印する為の大掛かりな仕掛けだったと昨日初めて聞かされた。 知って、驚愕し、また、納得もした。 人ならざる存在、有機ヒューマノイドタイプインターフェース、だが、心無きものではない。長門は、万能でありながら、精神は生まれたての子供のようなものだった。だから経験を重ねるごとに成長していった。長門と時間を過ごすうち、俺は情調の萌芽を見た。だが発露は微弱でいつまでたってもその顔には能面が光の加減によって浮かべる程度の情動しか宿さず、機械の音声ガイドなみの慎ましやかな音調でしか言葉を発しなかった。 長門がヒューマノイドだからといって人と劣っているとは思えない。これは個性ということなのだろう、と自分を納得させていたのだが、どこか釈然としなかったのも事実だ。 表情が乏しいのから分かり難いかもしれないが、長門は元々感受性は豊かな方だった。だから、色々な感情を表に出す少女のはずだ。そう思った心の裏にはあの改変世界の内気な少女の面差しがあったのかもしれない。 だから、感情を封印したのだと言われて得心がいった。 人として当然抱えるべきもの、それを持って初めて人間のスタートラインに立つんだ。そんなものはバグでもなんでもない。持たないことの方が欠陥なんだ。作り物ではない、生けるものの宝だ、捨てるだなんてとんでもない、お前は間違っている。…と、説教すべきところだっただろうが、俺は、捨てたことが間違いだったと気付いたことの方に感動していた。 捨ててもなお、再び湧き上がった感情、長門の、人としての成長がそうさせたんだ、ってな。 ふわりと風が舞った。 盛りを過ぎた桜が、花弁をはらはらと零す。 「大丈夫?」 今まで聞いたことのない、まろみのある声が背後からする。振り向くと、街灯と月明かりが、こちらに手を差し伸べる少女の姿を浮かび上がらせた。かれこれ4年、付き合いがあるが、昨日…いや、数分前とは纏う雰囲気がまるで違う。 深く、溜息を吐く。 俺は立ち上がってから、万感の思いを込め、その手を強く握った。 「…おかえり、長門」 長らく手放していた心を取り戻した少女は、その意志の強さを残した目を三日月形に歪め、はにかみに頬を染め 「ただいま」 −終− 5月に無料配布本にしたお話。長門さんを微笑ませてみよう企画。…何のこちゃ。一応イラストも描いたのですが、三年後で制服姿は間違いだと気付いたのでチラ見せ。 |